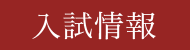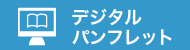SS国内研修「ブナとヒトの共生研修」を実施しました
令和7年7月22日(火)~7月25日(金)、秋田市地蔵田遺跡、マタギ資料館、青森県西津軽郡深浦町十二湖・千畳敷・三内丸山遺跡にて、高校2年生11名が参加し、研修を行いました。研修の中心である白神山地の十二湖周辺で現地ガイドの柳町明男先生のご指導の下、2日間の実地研修を行いました。
1日目はまず、秋田空港からすぐ近くにある地蔵田遺跡を見学しました。この遺跡は旧石器から、縄文、弥生時代までの長い期間について、ここで生活する人の姿を知ることができる貴重な遺跡です。昭和60年に発掘され、現在は遺物資料館と復元遺跡公園からできています。学芸員の方から出土した様々なものや復元された竪穴式住居の案内、説明をいただき、質問にも丁寧に対応いただきました。
次にマタギ資料館を見学しました。館長さんから阿仁マタギの生活や歴史、様々な道具などの説明をいただきました。雪深い山奥に住む人々が自然と共生する中で育んだ知恵や文化を学ぶことができました。たくさんの熊の剥製はどことなくユーモラスですが、今年も各地で起こっている熊による被害について考える機会にもなりました。
2、3日目は柳町先生の案内で白神山地の実地研修を行いました。ナラ枯れの処置のために切り倒され、ビニールに覆われた木々がたくさんあり、温暖化によるナラ枯れ被害の北上、環境の変化がおこっている現状が最も印象に残りました。また、食用や薬になる植物を教えていただき、大きなブナの木の直径を測定する中で、山の豊かさを実感しました。夜の講話では、柳町先生の生活や生き方に、自然を無駄にせず、再生していく先人の知恵や文化を、そして、ここで生きてきた人でないとわからない多くのことを学びました。
4日目は十二湖エコミュージアムを観覧し、2日間のフィールドワークで学んだことを深めました。その後、十二湖駅前の「けやぐの家」に立ち寄らせていただきました。今回体調をくずされて、ガイドしていただけなかった板谷正勝先生が申し訳なさそうにしながら、歓待してくださいました。マタギとして生活されてきた先生の手作りの装備品、毛皮で作ったチョッキなどを見せていただきました。北金ヶ崎の千畳敷海岸、日本一の大銀杏、日本最大級の縄文集落である三内丸山遺跡で研修を終え、無事帰ってくることができました。
自然を守る、人の生活を守る、その両立がこの地域で続けられてきた共生の姿なのでしょうが、今、その営みを続けていくことの難しさや問題点を参加生徒は本研修を通して、気づいたのではないかと思います。