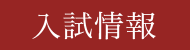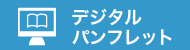SS国内研修「東京海洋大学「海の科学」研修」
令和4年8月4日(木)と5日(金)、本校にてオンライン形式で国内研修を実施し、高校2年生1名が、東京海洋大学の岩田繁英先生、小山智之先生、川辺みどり先生、中村玄先生、三島由夏先生による以下の講義を受講しました。
①「水産資源を持続的に利用するために~魚を知る、獲る、管理する~」岩田繁英先生
魚を持続的に利用するために何をすればよいかを学びました。海の資源量を推定する評価方法や、魚を獲るさまざまな方法、個体数管理のための指標などが講義の中で解説されました。
②「海の生き物がつくる健康機能成分」小山智之先生
食品に含まれる栄養成分や働きについて解説されました。和食の基本食材の一つである魚介類に含まれる成分(DHPやタウリンなど)の特徴や健康機能について教えていただいた他、生物が作る成分をヒトの健康維持に利用していくために、自然の恵みに感謝しつつ、大切に守っていかなければならないことを学びました。
③「これからの海洋科学と、社会のつながり」川辺みどり先生
海洋科学とはなんだろうかということをテーマに様々な方面からの解説がありました。海洋資源を守っていくためには、行政や専門家だけでなく、社会全体が参加して情報収集や管理に関わっていくことが大切であることを学びました。
④「鯨類学入門」中村玄先生
クジラを生物学的な視点から多面的に解説されました。クジラの耳垢には年輪のように年齢が刻まれています。これは、冬季は温暖域に、夏季は寒冷域で生活をする1年サイクルがあるために生じることなどを学ぶことができました。
➄「海洋生物の音と人為雑音」三島由夏先生
さまざまな海洋生物の出す音や海洋生物の可聴域についての解説がありました。また、エコロケーションについての紹介もあり、海洋生物にとっての音の大切さを学ぶことができました。人間が出す人工的な音(人為雑音:大型船、鉱物掘削、くい打ちなどの音)は、海洋生物の可聴域と周波数帯が重なっています。このことが生物に与える影響を調査し、問題点を解決していかなければならないことも学びました。
感染症拡大防止策のため、今年度もオンライン開催となった高大連携講座としての研修でしたが、講義を通して、「海洋」について深く考えることができたようです。「海洋」のどの部分を取り上げるかで、全く異なるテーマになるということを知るよい機会ともなりました。