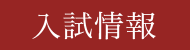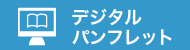北限サンゴの産卵研修
令和5年8月28日(月)~令和5年8月30日(水)の3日間の日程で、静岡県沼津市西浦平沢「平沢マリンセンター」を中心に、川嶋尚正先生(静岡県内水面漁業協同組合連合会)、 中村雅子先生(東海大学海洋学部)、朝倉一哉先生(平沢マリンセンター)のご指導の下、以下の内容で研修を行い、高校2年生の7名が参加しました。
①講義「北限サンゴ群落の変遷と魚群相ついて」の聴講
伊豆半島の西岸にのみエダミドリイシの群落が生息している理由について、川嶋先生とのやりとりを通して理解することができました。またサンゴ群落では岩礁域に比べて、熱帯由来の季節来遊魚が多く、これらの魚はサンゴへの依存度が高く、サンゴが生物の多様性に大きな影響を与えていることも学びました。
②講義「サンゴの生活史について」の聴講
サンゴは共生者である褐虫藻と「相利共生」の関係にあることを知ることができました。これはサンゴが褐虫藻を外敵から保護する代わりに、褐虫藻はサンゴに必須アミノ酸を供給することで成立しているからです。またサンゴの産卵形態や、成長するまでの過程も学ぶことができました。
③講義「海の環境保全の取組」の聴講
SDGs にも掲げられる「海の豊かさを守ろう」という目標を達成するために、平沢マリンセンターが行っている取組を教わりました。生物多様性の象徴である「サンゴを守ること」が平沢マリンセンターのビジネスを持続可能なものにするために大切であることを理解することができました。
④ 実習「シュノーケリング技術習熟訓練」
実際に海中でサンゴを観察しました。前日の講義で聴いたとおり、サンゴの周りには多くの魚が生息していることを確認することができました。
⑤ 体験・見学「陸上水槽のサンゴの観察・灯火採集」
水槽のサンゴでは残念ながら産卵は確認できませんでしたが、灯火採集では多くの微生物が集まってくることを確認することができました。
⑥ 調査「魚群相・付着生物の調査」
岩場と砂場に分かれて、観察できる魚の違いを調査しました。水中で記録したり、その後、お互いの調査結果を報告するなど、全力を挙げて取り組むことができました。
本研修では、参加した生徒たちは、奈良県ではできないとても貴重な経験ができました。特に魚群相の調査では、生徒達は一生懸命に海の中を観察して、調査を行いました。北限の海の生態系が作り出す美しさに魅了されたり、また講師の先生も非常にフレンドリーで、生徒達にも温かく接して下さいました。これらのことは、生徒達の研修がより実りの多いものにつながるものでした。