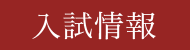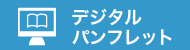東京海洋大学「海洋学」研修
令和5年7月31 日(月)~8月3日(木)の3日間の日程で、東京海洋大学で実施される高大連携公開講座「海の科学」の受講を中心に以下の内容で研修を行い、高校2年生6名が参加しました。
(1) 東京海洋大学「海の科学」講座の受講
①「沿岸域利用形態としての海洋性レクリエーション」千足耕一先生
海水浴や潮干狩りなど、私たちが「娯楽」として海洋を利用する一面について多面的に学習しました。海洋性レクリエーションの歴史と時代背景、現代の課題として漁業・遊漁・マリンスポーツの並立に必要な工夫などについて解説していただきました。
②「海洋危険生物:食べて中毒、刺されて被害」永井宏史先生
海洋生物の危険性について、おもに毒に注目して解説していただきました。食することで中毒を起こす生物とその症状や原因、サメなどの物理的な危険のある生物や、クラゲなどの毒をもつ生物について、総論的に学習することができました。
③「水産資源を持続的に利用するために~魚を知る、獲る、管理する~」岩田繁英先生
魚を持続的に利用するために何をすればよいかを学びました。海の資源量を推定する評価方法や、魚を獲るさまざまな方法、個体数管理のための指標などを解説していただきました。
④「海の生き物がつくる健康機能成分」小山智之先生
和食の基本食材の一つである魚介類に含まれる成分の特徴や健康機能について教えていただきました。生物が作る成分をヒトの健康維持にうまく利用するためには大切に守っていかなければならないことを学びました。
➄「海洋生物の音と人為雑音」三島由夏先生
さまざまな海洋生物の出す音や海洋生物の可聴域についての解説がありました。人間が出す人工的な音は、海洋生物の可聴域と周波数帯が重なっており、これが海洋生物に与える影響を調査し、問題点を解決していかなければならないことを学びました。
(2) 船の科学館「南極の氷」研修
南極観測隊が観測所に到達するまでの苦労や現地での生活について、実際に南極観測に5回赴いた学芸員から講義を受けました。実際に南極から採取された氷のようすなどを観察しました。南極観測船「宗谷」内を見学し、さまざまな設備や工夫について解説を受けることができました。
(3) マクセルアクアパーク品川 職業講話
開館前に実際に勤務されている飼育員の方から、どのようなキャリアパスを歩んでこられたか、どのような苦労があるかなどをお話いただきました。講話の後、実際に水族館内を見学し、実際の生物の生態をいかに印象づけるかといった展示の工夫なども学びました。
本研修において、普段の生活は海とはかなり離れたものである生徒たちにとってはすべてのことが新鮮でもあり、「海洋」というテーマでもさまざまな学問が派生していること、科学のさまざまな分野が複合していることを実感できました。