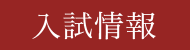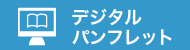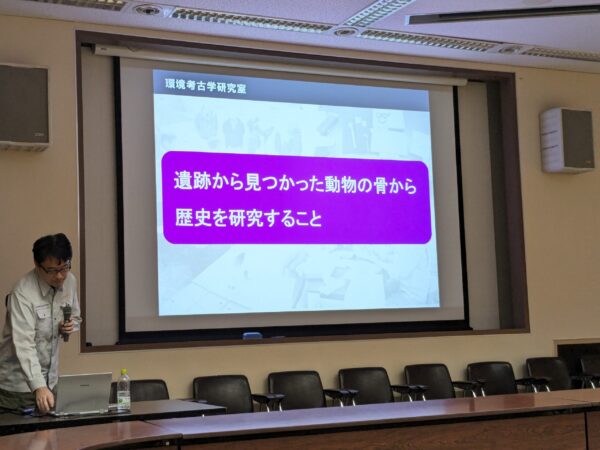奈良学ゼミ「文化財×自然科学:奈良文化財研究所における文理融合型研究-年輪年代学・動物考古学編-」
令和6年7月22日(月)、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所において、以下の内容で、奈良学ゼミを実施し、計14名の中高生が参加しました。
①講義「年輪年代学と動物考古学」
年輪年代学の講義では、植物の幹につくられる年輪は、時間分解能が高く、いろいろなデータを重ね合わせるといつの年代の年輪かを確定させることができることを学びました。また、夏の気温や結実数によって年輪の幅が変化することや、どの地域で育った樹木なのかがわかったり、木簡の年輪を調べることで復元にも役立てられたりすることなどが紹介されました。その調査にはCTスキャンなどの科学技術などが用いられていることも紹介されました。動物考古学の講義では、貝塚から見つかった骨のかけらをつなぎ合わせてどのような生物であったかを復元する作業について学びました。たくさんの標本から同じ生物の骨を特定し、その骨格を再現していくという作業に圧倒されました。また、復元された動物から、当時の人々が使っていた狩猟道具などが推定できたり、生活のようすなども解明できることに興味が深まりました。
②研究室見学「年代学研究室」
実際に年輪年代学を研究されている研究室を見学させていただきました。研究室の前には実際に大きな木の幹の輪切り標本があり、年輪を実際に数えられるようになっていました。研究室の中では、実際に出土した木簡などを見せていただき、コンピュータで年輪をスキャンして分析する手法などを教えていただきました。
③研究室見学「環境考古学研究室」
実際に動物考古学を研究されている研究室も見学させていただきました。出土品から非常に細かい動物骨や貝殻などを拾い上げ、実際にマグロ1体の骨格をまるまる組み立てて再現した標本なども見せていただきました。研究室の奥では動物の剥製をつくる作業をされていたので、その様子も見ることができました。
このゼミを通して、参加した生徒は、実際に出土した木簡や骨片など、教科書でしか見たことがない標本を目の当たりにしてわくわくした気持ちを抱いたり、考古学と自然科学という、一見まったく 別の分野に見える学問が非常に密接に関連していることを実感することができました。