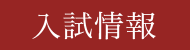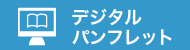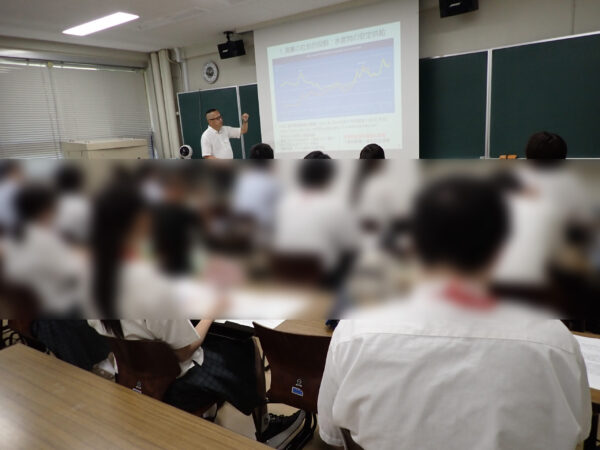SS国内研修「東京海洋大学連携 海洋学研修」を実施しました。
8月5日(火)~8月7日(木)の三日間,東京海洋大学品川キャンパス、船の科学館にてSS国内研修を実施し,5名の高校生(一年生3名、二年生2名)が参加しました。
一日目と二日目は,東京海洋大学品川キャンパスにて「高大連携公開講座『海の科学』」を受講しました。
○「水産資源を持続的に利用するために」(海洋生物資源学科 岩田繁英先生)
水産資源としての“魚”を持続的に利用するために,“魚”を知る、“魚”を獲る、“魚”を管理するという三つの観点から考えるという内容で、適切な水産資源の管理とは何か?という課題に取り組みました。
○「海の生き物がつくる健康機能成分」(食品生産科学科 小山智之先生)
食の健康機能を考えるために「食品の働き」「魚介類と食品成分」「健康機能成分の探索」「生き物を育む海」の4つのテーマで、生き物やその成分について、学びました。「健康機能成分の探索」では、ご専門の研究を紹介され、難しい内容でしたが興味をそそられるものでした。
○「漁業の社会的役割と今日的意義」(海洋政策文化学科 工藤貴史先生)
食料の安定供給を担うこと、持続可能な社会を構築していく産業という点から漁業を考えました。また、漁業は自立性が低く、さまざまな制約があるという特色をもちながら、地域の社会経済を支えていく産業として存在意義が高まるという点について、課題に取り組みました。
○「海洋環境保全を目指す海洋生分解性プラスチックの研究」(海洋環境科学科 石田真巳先生)
化石資源(石油)から作るプラスチックの基礎から生分解性プラスチックの研究について学びました。特に近年、海洋マイクロプラスチック汚染が環境問題の一課題として取り上げられる中、最新の研究内容について学びました。
○「地質学・古生物学・地球化学の使いドコロ」(海洋資源エネルギー学科 古山精史朗先生)
「海の科学」というテーマの公開講座ですが、主に地学(地質学)の分野からアプローチされた内容でした。化石を例に「知っておくと街中や世界中で楽しめる」という観点で講義が進められました。
一連の講義を通じて参加した生徒たちは,多くの知識を吸収し,科学的に「海」を見て考えることの大切さを実感することができたと思います。いずれの講義内容も知識習得にとどまらず、本来フィールドワークと合わせて研究を進めていくものであり、かつ短期間ではありましたが,大学講義の聴講という,普段では得られない貴重な体験をすることができました。
三日目は船の科学館(初代南極観測船「宗谷」)にて、学芸員の髙橋義行さんによる案内で「海と船の文化」をテーマとした研修をおこないました。
はじめに、日本で初めての南極観測船「宗谷」に乗船、「旧士官食堂」にて、「宗谷」の歴史を学びました。合わせて「南極の氷」を見せてもらい、実物に触れ、氷の融ける「音」を聴きました。氷は1,000万年も前の大気(ちなみに人類の誕生は30万年前)を含んでおり、これもまた貴重な体験をすることができました。
その後、髙橋さんのわかりやすい説明に合わせて船内を見学し、普段見ることができない甲板の一部や操舵室裏の部屋も紹介してもらい、当時の船のようすについて学ぶことができました。
現在の快適な船旅に比べて、過酷な環境の中で南極観測に向かう人々の苦労が理解できました。
今回、講義形式中心の研修でしたが、「海洋学」というテーマを超え、とても幅の広い内容を扱いました。参加した生徒たちにとって,この研修が今後の学びへの原動力になってくれることを期待したいと思います。