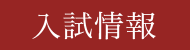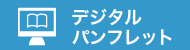学外サイエンス学「京都大学文学部文学研究科 斑鳩フィールドワーク」
令和4年11月22日(火)、京都大学の吉川真司先生をお招きして、「古代斑鳩の土地計画を実際に現地で体感する」をテーマとして学外サイエンス学習を実施し、高校1年生32名が参加しました。
吉川先生の講話を聞きながら斑鳩地区を実際に歩いて古代の様子を学び、体感するフィールドワークを行いました。まず、本校からバスにて法隆寺まで移動した後、法隆寺、仏塚古墳、法輪寺、法起寺と徒歩で移動し、現地調査を実施しました。
- 法隆寺では、最初、南大門→西へ進む→南西の角→北へ進む→西大門と歩きました。この道は、聖徳太子一族が蘇我氏により滅亡した後に造成された道で、真北に対し西へ8°傾いていることを学びました。法隆寺が7世紀後半に再建されるときはこの道を残す形で建立されたこともわかりました。次に、西大門→東大門へ向かいながら途中、西院伽藍、宿坊、大宝蔵殿について実物を目の前にしながらその用途などを学びました。
- 法隆寺の次に貯水池→仏塚古墳と歩きました。貯水池の土手から飛鳥方面を望むと、飛鳥から法隆寺へと聖徳太子が通っていた道が真北から20°傾いて現存する道であることも目の当たりにできました。また、仏塚古墳では石室の様子を覗いて確認しました。
- 法輪寺では、十一面観音をはじめとする仏像が安置された講堂を見学し、このあと古代の井戸「三井」に寄り、井戸の構造も確認しました。
- 最後に、法起寺まで歩き、周辺の条里制のあとを見学しました。1町=109mで画される古代の条里が非常に美しく残っているのを確認し、条里1区画は5人分として支給された土地であることを学び、その広さを歩いて実感することができました。
本研修に参加したのは、日本史を詳しく学んでいない生徒たちではありましたが、講師の先生の分かりやすい解説のおかげで、深く歴史を学ぶことができました。現地でのフィールドワークにより、教科書だけの学習では摑みきれないイメージや感動などを得ることができたようです。