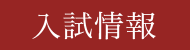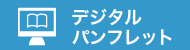SS国内研修「「水源地の森」保全研修」
令和4年11月27日(日)、奈良県吉野郡川上村の「森と水の源流館」および「水源地の森」周辺及び吉野林業人工林にて、森と水の源流館の古山暁先生と吉野かわかみ社中の上嶌逸平先生のご指導の下、以下の内容でSS国内研修を実施し、事前学習を行った高校2年生8名が参加しました。
①事前学習 11月23日YouTubeLive視聴
第22回共生科学研究センターシンポジウム・第26回紀伊半島研究会シンポジウム『樹と水と人の共生を未来へつなぐ』」を視聴し、森林と人間の関わりや人口1498人の川上村の自然環境を学び、疑問や仮説をたてて当日の研修への準備をすすめました。
②見学「森と水の源流館」
これまで川上村で行われてきた「川上宣言」に代表されるような環境保全の取組の展示見学および源流の森シアターでパノラマ映像を視聴しました。保全の大切さや四季を通しての森の変化、ダイナミックな生物の営みを感じとることができました。
③講義・見学 創業130年の老舗料理旅館「朝日館」
バスでの移動途中、車窓から川上村の景色をみながら歴史や地形の講義を拝聴しました。また「朝日館」の見学を通して暮らしている人々の生活の様子やその距離感を体感することができました。
④フィールドワーク「水源地の森」
実際に、森林保全のために川上村が買い上げて手つかずの原生林として保護する水源地の森を訪れ、自然のままの森林がどのようなものか、その神秘的な美しさも含めて実体験しました。昼食は「地域の文化を味わう」ということで、あまごの甘露煮や鹿肉のハンバーグなどを食し、自然の恩恵を享受しながらこの地で生きてきた人々の知恵についても学びました。
⑤講義・実習「チゴロ淵」
吉野杉の人工林の中で吉野地域の林業のなりたちや歴史についての講義を拝聴しました。水源地の森でみた自然林と人工林のちがい、機械化の難しさ、これからの林業のあり方についてなどの説明をいただきました。
今回、たまたま老舗旅館の中を見学することができたこと、地元食材によるお弁当を食べたこともあって、人々の暮らしと自然の密接な関係を感じとることができたと思います。水が生まれる源流のある川上村。自然保全の大切さと同時にクマの出没件数の増加、過疎化対策など人と自然の共生の難しさに気づくことができました。